経済危機に苦しむヨーロッパ各国を尻目に、ドイツ経済は好調だ、と朝日の記事が伝えている(5月2日朝刊)。ダイムラー・ベンツでは、昨年、過去最高の210万台の売り上げを達成し、膨大な利益をあげたとして、従業員一人当たり4100ユーロの一時金を支給するほどだった。ダイムラーに限らず、他の自動車メーカーも、同じような好景気に沸いているそうだ。
経済学と世界経済
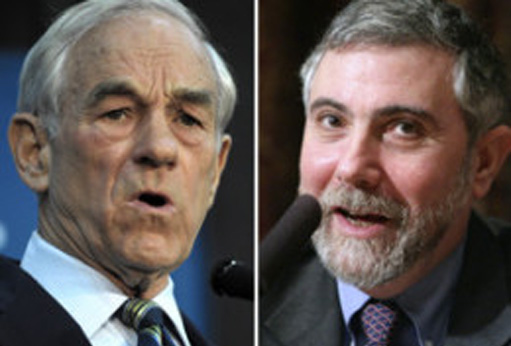
ブルームバーグのテレビ討論会で、エコノミストのポール・クルーグマンと共和党の議員でかつ大統領補選のランナーだったロン・ポールが、アメリカの金融政策のあり方を巡って、すさまじい論戦をしたそうだ。ふたりとも名前にポールがついているので、この論争は、ポール対ポール論争と呼ばれた。
クルーグマンの「世界大不況からの脱出」(三上義一訳、早川書房刊)は、1999年の「世界大不況への警告」を下敷きにして、リーマンショック後の世界的な大不況について併せて論じたものだ。前著では、1990年代におきた中南米やアジア諸国の大不況について、なにがそれらを引き起こしたのかを論じた。そこでの論点は今回の世界大不況にもそのまま当てはまる、とクルーグマンはいう。

米金融大手シティグループの株主が4月17日に、パンディット最高経営責任者(CEO)に1500万ドルの報酬を支払う案を株主総会で否決したと、ロイターが伝えている。この報酬案は、CEOの報酬を金融危機以前の水準に戻そうとするものであったが、55パーセントの株主が待ったをかけた。理由は、シティグループの業績が業界基準を達成してこなかったというものだ。
筆者が手にしている日経ビジネス文庫版の「クルーグマン教授の経済入門」にはおまけがついている。「日本がはまった罠」と題する小論だ。この小論の中でクルーグマンは、90年以降に日本が陥った深刻で長引く不況について、その本質や原因、そしてそこから脱出するには何が必要かについて論じている。
2008年のリーマンショックが、市場原理主義といわれるものの産物であったことは、今や広く認められている。市場原理主義とは、市場の持つ調整力を盲信して、政府による規制を最大限なくそうというものだ。そうすれば、経済は自然とうまくゆく。そう考えるわけだ。
ユーロ圏の一部諸国におけるソブリン危機問題や、アメリカの政府債務支払い危機問題を通じて、財政赤字の問題が大きくクローズアップされた。日本もその例外ではないので、このまま放置しておくと大変なことになるから、いまのうちに消費税を増税して、財政赤字を解消する努力をしなければならない。それができなければ、日本は市場によってアウトを突きつけられ、やがて破滅の道をたどることになるだろう。こんな半分脅迫ともいえる論調がまかり通っている。
「クルーグマン教授の経済入門(日経ビジネス文庫版)」を読んだ。ポール・クルーグマンが一般読者向けに書いた初めての入門書を、山形浩生という一風変わった人が日本語に訳したものだ。一風変わっているというのは、訳し方が尋常ではなく、ふざけ半分のような印象を与えるからだ(橋本治氏の桃尻語の影響を受けているらしい) しかしけっこう読みやすく訳せている。
小野善康氏は、株価の変動が景気に及ぼす影響を認めたうえで、株価の水準は必ずしも経済のファンダメンタルズとは関係のないところで決まる、したがってバブルが発生して景気が過熱気味になったり、逆にバブルがはじけて深刻な不況に陥ったりするという。(小野善康「景気と国際金融」)
小野善康氏は国際金融の分野でもユニークな見解を展開している。ここでも氏は、主流派経済学が想定している前提が実態とはかけ離れていることを指摘しながら、議論を展開する。以下その議論を「景気と国際金融」(岩波新書)によって、追って行こう。
小野善康氏が展開する国債論は非常にユニークだ。国債というものは、現役世代にとっては国の借金が増えて国家経済が危うくなることを意味し、将来の世代にとっては過去のツケを支払わせられるという点で、世代間の対立の種になる、といった理解が一般的だが、小野氏はそれを否定し、国債というものは、国民経済の中で右から左へとお金を移動させるだけで、国民経済全体にとってはプラスにもマイナスにもならない、また将来世代へのツケまわしも、必ずしも起きるとは限らない、と主張する。こうした主張は従来の経済理論とはあまりにもかけ離れているので、筆者の友人で経済学を研究している男などは、奇矯な理屈だと批判している。
小野善康著「景気と経済政策」(岩波新書)を読んだ。小野さんの経済学の特色がコンパクトにまとめられていて、非常に啓発された。その特色とは、供給側の経済学と需要側の経済学という一見対立関係にある二つの学説を、どちらかを絶対化するのではなく、それぞれに応分の価値を認めようというものだ。そして平成不況と呼ばれるような、長くて深刻な不況局面においては、需要側の経済学により多くの出番がある、小野さんはそう考えるのだ。
小野善康氏はユニークな不況動学論を展開しているそうだが、その理論はケインズ理論の批判的検討を通して生まれてきたようだ。この本は、氏のケインズ批判の要点と、それを踏まえた上での不況克服のための処方箋を示している。非常に薀蓄のある議論だ。
アメリカの金融危機やEUの債務危機に直面して、今まで大繁栄を誇っていた新古典派経済学が評判を落し、一時は青息吐息の状態だったケインズ経済学が見直されるようになったが、どうも、そのケインズ経済学でも、今起きている事態、とりわけ日本の長期不況のような現象を説明できていない、説明できないから不況脱出に向けての的確な処方箋も書けない。いったいどうなっているのかね、というのが筆者のような経済学音痴の正直な感想だった。

日米欧の先進諸国でちょっとした金融バブルというべき状況が生じている。株価の上昇や国債価格の下げ止まりといった事態だ。このことの背景には、各国で行われている超金融緩和がある。その中に、アメリカ連邦準備制度によるインフレ・ターゲットの表明、それに促された日銀のインフレ誘導政策があることはいうまでもない。
大瀧雅之「平成不況の本質」を読んだ。副題に「雇用と金融から考える」とあるように、この本は平成不況と称されるものが、主として雇用の破壊と云う形で現れ、それが消費の縮小を通じて経済のさらなる縮小と云うマイナスの循環をもたらしてきた一方、企業所得のほうは一貫して拡大してきたことを説明している。
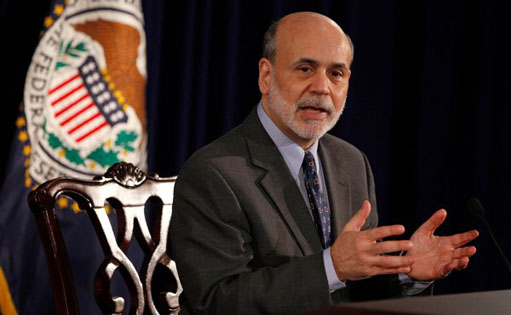
FRBのバーナンキ総裁が、現在実施中のゼロ金利政策を少なくとも2014年いっぱいは継続すると表明した。デフレ傾向の中で長引く不況を意識したものだ。バーナンキ総裁は併せてインフレ目標を2パーセントに設定し、その実現のために必要なら、貨幣の供給量を増やす方策としてのQE3を実施する可能性にも言及した。
ロナルド・ドーアといえば日本研究で有名な社会学者だ。筆者も若い頃に「学歴社会~現代の文明病」などを読んだことがある。1925年生まれと云うから、80歳をとっくに超えている。そんな氏が「金融が乗っ取る世界経済~21世紀の憂鬱」と題して、この20-30年ほどの短い間に世界中で進行した金融資本による経済の制圧と云う現象を、嘆かわしい事態として描き出している。老体にムチ打って慨嘆せざるを得ないほど、この現象は度が外れて異常だというのだ。
経済学史の名著として知られる宇沢弘文氏の労作「経済学の考え方」を再読した。世界規模の経済危機が深刻化し、1930年代位以降最大の経済恐慌も懸念されている現在、経済学がこうした事態に有効な対策を打ち出せないでいるのは何故なのか、その手掛かりを経済学の歴史のなかに見出そうとして、この本を再読した次第なのであった。危機の時代にあってこそ、歴史から学ぶべきものは多いと考えたからだ。
本日
昨日

最近のコメント